実績紹介
中国新聞社様に聞く~AWSによるIxAプログラムで、生成AIを活用した新サービスを企画した2日間とは?
株式会社 中国新聞社様
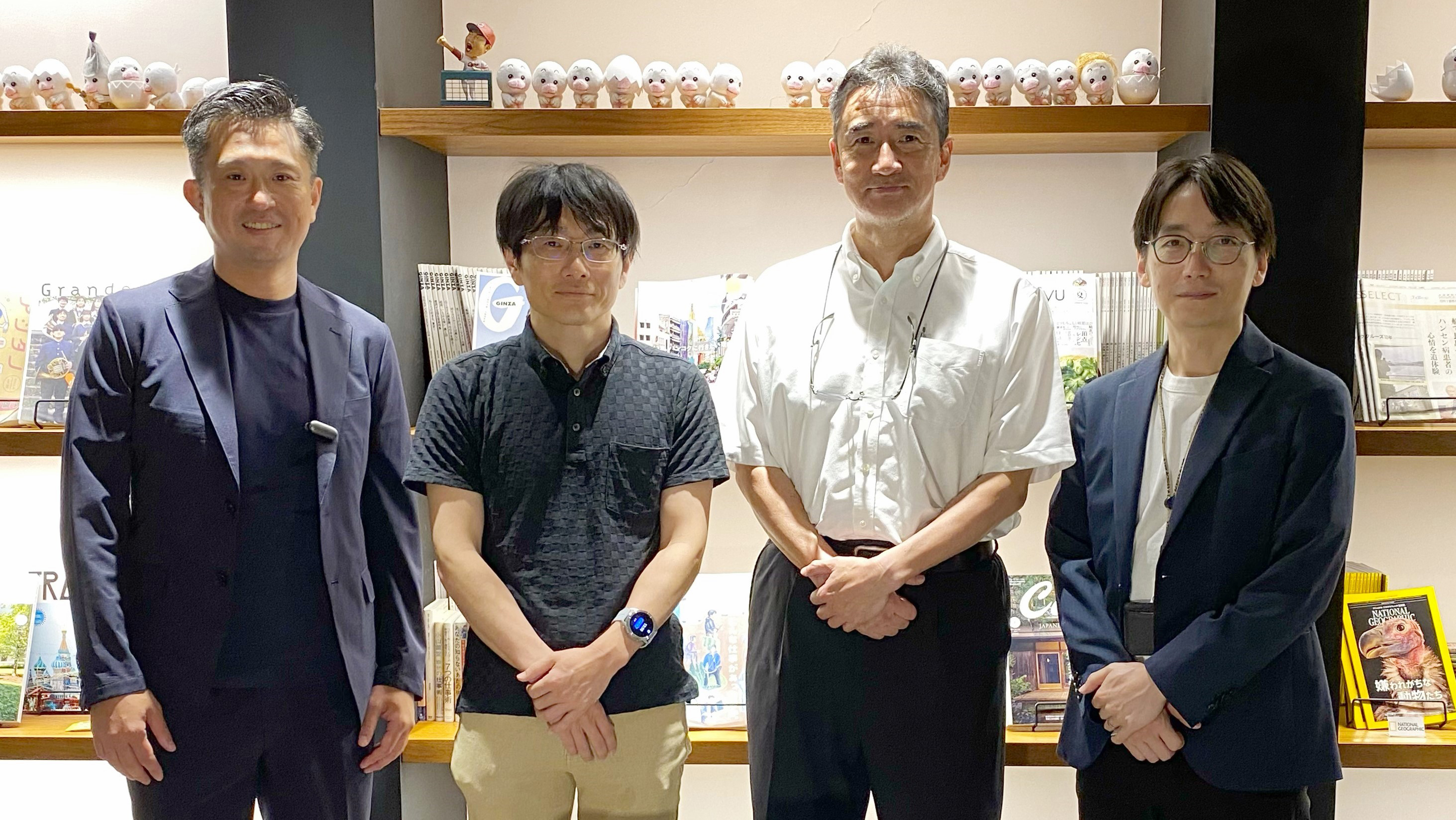
Amazon の”Working Backwards” というフレームワークをご存知でしょうか?
これは、AmazonやAWSが主要なプロダクトや新規事業を立ち上げる際に必ず実施する、お客さまを起点にしたサービス・プロダクト開発プロセスです。そして、このプロセスを用いて、実際のサービス・プロダクト考案を進められるのが、アマゾン ウェブ サービス(以下、AWS)が提供するIxAプログラムです。
このプログラムにご参加いただいた中国新聞社様に、プログラムでの体験や、得られたものについてお伺いしました。
<お話を伺った方>
株式会社 中国新聞社 メディア開発局次長 片山学様
メディア開発局 明知隼二様
技術局 システム部 水田行則様
「お客様を起点に考える」を体感し、具現化した2日間
山田:今回、中国新聞社様には、色々な部署から6名の方に参加いただきました。当社もPoC技術支援パートナーとして中国新聞社様と一緒にプログラムに参加しました。
IxAプログラムでは、Amazonのサービス・プロダクト開発プロセス ”Working Backwards” を実際に活用して、新しいビジネスを構想します。
今回は、中国新聞社様が記事を作成する際のプロセスに生成AIを取り入れるという新サービスを検討され、最終的にはPoCが開始できる一歩手前ぐらいまで、企画を練っていただきましたね。
このプログラムでは、まず事前に今回取り組む課題をどう設定するか、メールでやり取りしながら決定。そのうえで2日間、目黒のAWS本社に集まっていただいて、座学を受けた後でワークショップを進め、最後にアイデアを具現化するためにブラッシュアップしていくという流れでした。
2日間、目黒のAWSのオフィスに缶詰めになって検討していただいたのですが、いかがでしたか?
片山様:経営、新規ビジネスの観点から複合的に新サービスを検討するため、メディア開発局、編集局のデジタル部門、情報システム部門にあたる技術局など、複数の部署から6名が参加しました。新規事業、サービスを検討するというプログラムですので、メンバーはそれぞれの業務に精通したメンバーを選抜しています。テーマは「デジタル版記事タイトル作成への生成AI活用」と設定しました。
得るものが多い2日間でしたね。こんなに頭を使ったのは、何年ぶりだろうというぐらい、よく頭を使いましたよ。(笑)
AWSの「Working Backwards」がどういうものかにも興味があったので、目黒に行ってその考え方を学ぶだけでも価値があるだろうと思っていましたが、実際その通りでした。

参加して得られたもの
山田:どんなものを得られたのでしょうか。
明知様:大きく二つあると思います。
まずは、局を超えて複数のメンバーで参加したことによる学び、そしてAWSの「Working Backwards」の考え方そのものを学んだことです。
水田様:私たちの部署では、技術面から新聞制作のプロセスを支える業務を担っています。
私はメディア業界外からの転職で社歴が浅いこともあり、生成AI活用に関する社内の議論で挙がった各局の課題について、概要は理解していたものの、その本質までは十分に把握できていませんでした。
しかし、今回のプログラムの中で少人数のワーキングチームによる課題の深掘りをしたことで、各局が抱えている課題をより深いレベルで理解し、問題の根本を把握することができました。これは大きな成果だったと感じています。
もちろんこれはこのプログラムでなくてもよかったのかもしれませんが、思わぬ副産物といえます。

課題を徹底的に掘り下げ、解像度を上げていくことで、アイデアが生まれる
明知様:「Working Backwards」については、書籍やウェブ上の記事などでも知っていたこともあり、もともと関心がありましたが、とても大きな学びになりました。※1
お客様起点で考えましょうというのはよく聞く話ですし、大事だよね、とも思っていました。
しかし、実際に組み立てられたプロセスを体験してみて、「お客さまの観点に立って考えるというのはここまでやるのか」と驚きましたね。
山田:「Working Backwards」は、顧客体験を起点として開発に取り組むため、「ワーキング・バックワーズ(逆向きに取り組む)」と名付けられているそうです。このプロセスを体感できたということでしょうか。
明知様:はい。実際にやってみると、その効果がよくわかりました。たとえば、ワークショップではまず、ワークシートを使って顧客像を具体化し、ひとつずつ課題を明らかにしていきます。そのプロセスに時間を割くので、「課題をどうやって解決するのか」という話が出てくるのは、プログラムの後半です。
徹底的に、困っている人が「何に困っているか」をひもとく--その手法を学び、体感できたことは大きかったと思います。
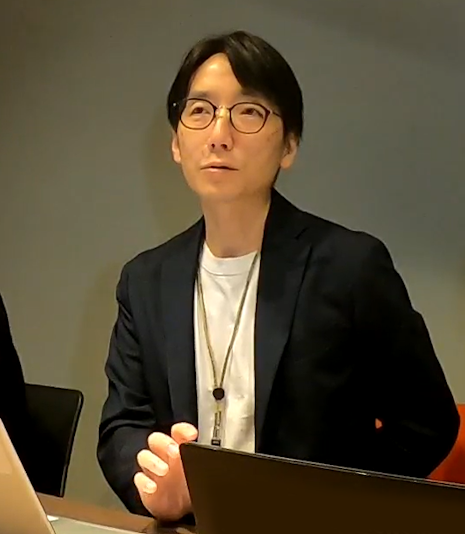
通常の会議による検討では生まれ得ないもの
片山様:プログラムでは、徹底的に「なぜ」を突き詰めていきました。「お客さまは誰か」「課題はなんなのか」「新しい可能性とはなにか」「最も重要なメリットとは」…などなど。そうやって解像度をどんどん上げていくプロセスは、具体的でとてもよくわかりました。単にぼんやりと「お客さまがほしいものってなんだろうね?」と考えるのではないんですよね。
通常社内で何か検討する際には、忙しいメンバーが週に一度集まって1時間の会議を行って、また1週間後に集まる…という流れになりますが、缶詰になってギリギリと考え、それによって生まれるものがあるということが、とても印象的でした。
山田:たしかに、意見が出なくなるまでそこからさらに絞り出す…そんなところまで突き詰めないと、出てこないものがありますよね。その中でも特に印象に残っていることはありますか?
片山様:面白かったのは「走りながら考える」というフレーズです。失敗を恐れず、走りながら考えて形にして、フィードバックをもとにブラッシュアップしていくという反復的なプロセスが重要であると。そういうプロセスが、市場のお客様のニーズに素早く対応して、良いサービスにしていく流れなのだ、ということが特に参考になりました。
失敗が良いものとまでは言いませんが、失敗を許して進んでいこうという考え方はAmazonの文化なんでしょうね。
生成AIを全社員で使おうという取り組みの中で、今回の参加を決定
山田:そもそも、なぜこのプログラムに参加しようと思われたのでしょうか。
片山様:当社では、2025年の春から、生成AIを全社員に使ってもらおうという取り組みを始めました。各局から計20人の社員を「AIトレーナー」として選出してもらい、その方々にまずはどんどんスキルアップしてもらうことを考えていたんです。
そんな環境整備の中で、NRIネットコムさんからプログラムへの参加を提案してもらったので、よいタイミングでしたね。
生成AI導入の初期段階では業務効率化が主な目的でしたが、それだけでなく、新しい事業の創出にも役立てたいと思っていました。だから全社への導入にあたっては、生成AIを単なる業務の補助ツールではなく、「我々のパートナーだ」と考えられるところまでを目標にしていました。そんな考え方に合致したことも、参加のきっかけでしたね。
山田:参加にあたって、社内ではどのように調整をされましたか?
片山様:社内で生成AIの導入について検討を開始したのは昨年の夏ごろでした。AIのサービスプロバイダに話を聞いたり、トライアルで数社と取り組みを行ってみたり。著作権の問題もあって、社内には懐疑的な見方も確かにありましたが、他社でも生成AIの活用が進むなど、周囲の環境変化も感じていました。
利用を促進するにあたって、まず弁護士さんとガイドラインを作ったんですよ。実はこのガイドラインは、初稿段階ではかなり抑制的なものでした。しかし経営層に相談するたびに、「もっと積極的に使えるものにせよ」という指示を受けまして(笑)。新聞社として個人情報などについては慎重になりましたが、経営層の「『駄目である』というガイドラインではなく、自由な発想で使っていけるものに」という言葉に動かされて、ガイドラインを完成させました。
そんな中でのIxAプログラムへの参加のお誘いを受けましたから、社内で経営陣や上席に参加を提案した際も、反対は全くなく、「どんどん学んで来い!」という状況でした。
明知様:IxAにスムーズに参加できた背景として、もう一つ理由があると思っています。全社での生成AIの活用推進を既に進めていたという面もありますが、そもそも自社会員基盤の構築やAWS Clean Roomsなど、AWSのビジネス活用をかなり進めていたということも大きかったと思います。その点も相まって、今回のIxAプログラムに参加することへのハードルがなかったのかなと思います。※2
山田:経営層が抑制的になるというケースはよく耳にしますが、その逆というのは珍しいですね。
ともにプロジェクトに参加したことで、即座にゴールに合った提案を受けられる
山田:このプログラムが、技術的な面で参考になったところはありましたか?
水田様:プログラム自体に技術的な要素はありませんでした。しかし参加後に、「じゃあ具体的にどうしていこうか」となった時に、一緒にプログラムに参加していたネットコムさんに、「AWSのこのサービスを使ってこんなことができますよ」と、技術的な要素をふまえて提案して頂けたのはとてもありがたかったです。
通常であれば、企画を立てた後、技術パートナー企業に内容を説明し、時間をかけて議論したうえで、やっとプロジェクトが始まります。しかし今回は最初から説明せずとも、課題もゴールも技術パートナー企業としてのネットコムさんと共有できていたというのは、一緒にプログラムに参加してもらったことのメリットだと思っています。
山田:ありがとうございます。お役に立てたようでよかったです。
それでは最後に、今後についてお聞かせください。
明知様:今回のプログラムを、社内でも実施したいなと思っています。それだけ汎用性があるものだったというか、フレームワークとして確立されていましたね。あれを社内の色々な場面で使えたら、力になるのではと思っています。
片山様:この春に本格的な検討を開始して、ようやく生成AIを活用する環境が整ってきたなという状況です。これからは、社内から集めたトレーナーと共に、知識を深めてスキルアップしていこうと思っています。
生成AIは、どんどん活用している社員もいるものの、使っていない社員も多数いて、温度差のある状況です。まずは身近なところから使ってもらうなど、推進していかなければなりません。
また、日進月歩どころではないスピードで進化していく生成AIの情報に、どうやってついていくかが今後の課題だと思っています。
山田:そこはまた当社がお役に立てればと思っています。(笑)
NRIネットコムとしては、お客様のデジタル領域における課題解決のためのベストパートナーとして存在していきたいと考えています。中でもAWSに関わる部分については、エンジニアとしてエバンジェリスト、ジュニアチャンピオンなど、非常に優秀なメンバーが在籍していることが特徴です。彼らがいち早く生成AIを始めとする技術進化の流れに乗り、会社全体を引っ張ってくれています。また、クラウドだけではなく、ウェブ、デジタル全般での潮流にも解決策を提供していきます。生成AIの活用が進んで、今まで見えなかった世界が見えてくることもあると思いますので、ぜひ今後も意見交換をさせて頂ければと思っています。
本日はありがとうございました。
※1 Working Backwardsに関する書籍
『アマゾンの最強の働き方──Working Backwards』
※2 中国新聞社様のAWS Clean Roomsの活用についての記事(MarkeZine)
地域のエコシステムを目指す、中国新聞社に聞くファーストパーティデータ活用とコラボレーションの現在地